「もっといい時代がやって来そうだ」。新しい千年紀を前に、誰もがそんな期待を抱いたようですが、21世紀に入って早くも3年が経ち、その間、国際的にも国内的にも大きな事件が相次ぎました。いい時代というのは、向こうからやって来るのではなく、人間の努力で作るものだということが、よく分かりました。学習院の教育理念はいろんな言葉で語られていますが、共通しているのはそういう努力をする人間を育てたいということです。そして、21世紀の教育が20世紀の厳しい反省に立脚すべきだという点でも、学習院各校の意思は統一されています。
20世紀を「進歩という幻想にとりつかれた100年」と批判する意見があります。進歩の最たるものは科学ですが、そのすべてが人間を幸せにしたわけではないのです。20世紀はまた戦争の世紀でした。戦争は科学を進歩させましたが、科学は戦争をより悲惨なものにしました。しかも犠牲者の大半はつねに子供や女性や年寄りです。太古の昔から、人間は戦争を通じてではなく、戦争が起こらないようにする努力を通じて、進化してきました。戦争による略奪から交易に移行することで、人間はアルファベットを工夫し、貨幣を発明し、シルクロードの上を商品だけでなく、宗教や学問・技術が交流しました。自由貿易は今日でも平和の基礎です。国際機開で利害を調整するというのも、戦争を避ける人間の英知でした。思い通りにならないからと言って、大国が国際機関をボイコットしたとき、だいたい戦争や紛争への道が開かれました。
スポーツも古典ギリシアの時代から、戦争を避けるための英知の結晶でした。オリンピックはその典型ですが、ワールドサッカーを機に、日韓関係が民衆レベルから劇的に改善されたことも、鮮烈な印象を多くの人に与えました。スポーツだけでなく、国を超え、民族を超え、宗教を超えた交流が、人間どうしの理解を深め、戦争を遠ざけることは言うまでもありません。外国人が日本語を覚えるとき、その人はおおむね日本に好意をもっています。そんな外国人に日本人が好意を抱くのは当然でしょう。その逆も真実です。私たちはふつう英語その他の外国語を、国際化する社会で学び、働き、そして生活するための「用具」として功利的に捉えていますが、本当の価値は「人間どうしの理解」という深いところにあるのです。
学習院の教育とは縁遠い話に聞こえるかもしれませんが、上に述べたことはまさに学習院の教育理念に関わることです。科学にも経済にも、「人間の幸せのために」という視座を与えたい。自分の幸せより他人の幸せを先んずるような人を育てたい。それはキリスト教やイスラム教における、隣人愛をもって神愛に応える思想にも通じますし、大乗仏教の慈悲の心にも通じます。自分の文化や宗教や価値を他人に強制するのではなく、各種の交流を通じて相手を理解し、多様なものの共生を図るような人こそ、21世紀の担い手にふさわしいのではないでしょうか。そうしたヒューマニティに立脚した多文化理解は、学習院の伝統的価値でもあります。私たちは基本的な人間の能力としての学力は重視しますが、学力だけでない「人間としての魅力」を、学習院らしさとして与えたいと願っています。
|
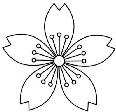 学 習 院
学 習 院
 21世紀の日本を担う人々 学習院長 田島義博
21世紀の日本を担う人々 学習院長 田島義博





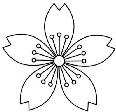 学 習 院
学 習 院
 21世紀の日本を担う人々 学習院長 田島義博
21世紀の日本を担う人々 学習院長 田島義博




