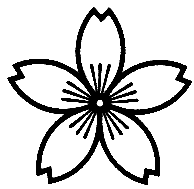 国劇部桜友会
国劇部桜友会
| 國劇部現役部員と卒業生の歌舞伎公演 | |
|---|---|
| 日 時 | 平成19年9月15日(土)開場11:30、開演12:00 |
| 会 場 | 浅草公会堂 |
| 内 容 | ・菅原伝授手習鑑 より 「賀の祝」 ・鬼一法眼三略巻 より 「菊畑」 ・仮名手本忠臣蔵 より 「七段目」 |
| 入場料 | 2,000円 |
| コメント | 國劇部は演じることで歌舞伎を深く研究しよう、という趣旨で活動を続けて今年で60周年を迎えます 現役部員は、年に一度の本公演を行っていますが今年は節目の年なので、卒業生と現役が合同で三幕を上演します。60年前の大先輩から今年の新入生までが世代を超えて熱演致します。 ぜひ、観にいらして下さい。 |
| 問合せ先 | pxm03705@nifty.com 菱倉真理(s64 史学科卒) |
|

 |
OB会長のひとこと 学習院国劇部OB会長 園田 榮治 (昭34政) |
素人の、しかも学生が「芝居の真似ごと」をすることにはいささかの抵抗もあった。しかし、「学生歌舞伎是非論」が一流批評家や関係者を交えて、冷やかし半分の新聞種になったりするのにも反発したくなる。 |
|---|

 現役公演大盛況
現役公演大盛況