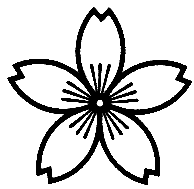|
ここ目白の地に明治41年(1908)に当時の学習院中等科・高等科が移転してきてから100年の時が流れた。今でこそ、目白といえば山手線の内側で交通至便な都心の一角となっているが、かつて学習院がここに移転してきた当初は、まだまだ東京郊外の田畑が広がる「片田舎」という言葉がぴったりの場所だった。
ではなぜ、どのような経緯でこの目白に移ってきたのか。
明治27年(1894)に東京は大地震に襲われた。その時、四ッ谷にあった学習院本館も大きな被害を受け、寄宿舎などを臨時教場として使用せざるを得なくなる。その上、周辺環境の変化などもあり、別の場所への校地移転の提起がなされた。
移転場所選考の段階では、現在の東京駅付近や荏原郡大森村(現在の大田区大森)、小田原など地方を含めて多くの候補が出ており、驚くべきことに富士山麓などもその候補地にあがっていたという。それらの中から明治29年(1896)9月、第7代近衛篤麿院長の時に、移転先に決定したのが北豊島郡高田村大字高田(現在の目白)だった。しかし財政上の問題により、工事は明治39年(1906)になって始まり、ようやく明治41年8月に目白の地に学習院が移転してくることになった。校舎などは移転翌年の明治42年(1909)に図書館(北別館)が竣工して、当初計画されていた建物はすべて完成した。足かけ15年の一大事業だった。
今、当時の様子を物語るものは、学習院大学史料館となっている北別館、乃木館、御榊壇、そして学習院の顔「正門」だ。
乃木館は、当時6棟あった寄宿舎の総寮部として建てられ、第10代乃木希典院長はそれまであった院長官舎ではなく、学生と生活をともにするため、ここに住んでいた。乃木院長逝去後は乃木館として昭和19年頃に現在地に移築されている。ちなみに、院長官舎の方は皇族寮として利用され、昭和38年に幼稚園建設の敷地を確保するために愛知県犬山市にある明治村に移築され、今でも当時の形で保存されている。
また、その乃木院長が明治43年(1910)に作った御榊壇は、明治42年7月14日に、目白移転後に初めて明治天皇が新校舎へ行幸されたことを記念したもの。この壇は前方後円墳を摸しており、周囲は不統一な石で組まれているが、これは当時の日本の領土の境界地から集めてきた80個の石を中心に作られたため。小さな御榊壇の中に、明治の日本が表現されているのだ。
そして100年目の今年4月には、大学院の人文科学研究科と自然科学研究科に、あわせて4つの新専攻ができ、新しい一歩を踏み出す。また6月には地下鉄副都心線「雑司が谷駅」も目と鼻の先の千登世橋下に開業する。今、目白キャンパスの内も外も大きく変わりつつある。
目白での1世紀、ここで明治の終わりに立会い、その後、関東大震災や第2次世界大戦をくぐり抜け、大正、昭和、平成の3つの時代を見てきた。そして、移転100年目の今年も新たな入学生を迎えた。 |