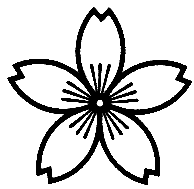

平成13年5月1日発行第78号より抜粋
 女子教育の伝統を支えた半世紀 女子教育の伝統を支えた半世紀 |
 第15回 オール学習院の集い開催 第15回 オール学習院の集い開催
|
|---|
| 女子教育の伝統を支えた半世紀 |
|---|
|
特集 ・ 短大 次世代への礎を作る |
|
学習院女子短期大学は、実質的には99年(平成11年)3月に97年(平成9年)度入学の学生(48回生)の卒業をもって幕を閉じ、最終の一年間は重なりましたが、その後四年制女子大へと移行いたしました。戸山キャンパスに、50年(昭和25年)4月に開学して以来、半世紀の歴史を経た短大も、今年5月頃には文部科学省の認可がおりて、正式に廃止となる予定です。名実共に学短が消えることになります。 |
|
そもそも短大の設立は、49年(昭和24年)の学校教育法が改正されたのを機会に、当時の女子高等科の父母による強い要望で実現したものでした。 |
| 昭和24年(1949) 25年(1950) 26年(1951) 27年(1952) 28年(1953) 29年(1954) 31年(1956) 32年(1957) 33年(1958) 34年(1959) 36年(1961) 37年(1962) 39年(1964) 41年(1966) 43年(1968) 44年(1969) 45年(1970) 46年(1971) 47年(1972) 48年(1973) 50年(1975) 52年(1977) 53年(1978) 54年(1979) 55年(1980) 57年(1982) 60年(1985) 61年(1986) 64年(1989) |
「学習院大学短期大学部設置認可申請書」を文部大臣に提出認可 小宮豊隆部長就任 開学式(文学科−国文学専攻・英語専攻) 戸山キャンパス正門、目白構内より移設 皇后陛下 行啓、授業参観 家庭生活科を開設 2年生に文学科から順宮厚子内親王はじめ14人が転科 第1回卒業式、卒業生73名、天皇皇后両陛下行幸啓 標準服制定 文学科を文科と改称 学習院女子短期大学と改称 家庭生活科の栄養士養成課程設置認可 旧3号館竣工 4号館(赤レンガ校舎)2階中央に大教室完成 門衛詰所設置 戸山講堂で短大独自の卒業式を挙行 安倍能成院長、短大学長を兼任 学生食堂開設 卒業生団体「草上会」発会式 新校舎(現2号館)竣工 栄養士養成課程を廃止 4号館(赤レンガ校舎)内に輔仁会部室設置 標準服廃止 第1回プレーデー 日高第四郎学長就任 増築校舎(現2号館)竣工 英語専攻を改組、I、II類を設置 4号館の大教室を改造、短大専用の図書閲覧室を開設 学習院女子短期大学学科転換認可申請書を文部省に提出 人文学科転換認可(文部省、短期大学に「学科」の設置を初めて認可) 人文学科と文化史専攻設置 5月4日を関学記念日に制定 10月やわらぎのつどい 児玉幸多学長就任 第1回和祭 学習院図書館戸山分館、短大図書館と女子部図書館に分離 1号館竣工 5号館竣工 磯部忠正学長就任 和寮開設 6号館竣工 図書館司書、学校図書館司書教諭課程を新設 第1、第2和寮閉鎖 近藤不二学長就任 学習院女子短期大学創立30周年記念式典 短大図書館(戸山図書館)竣工 小倉芳彦学長就任 互敬会館(3号館)、部室棟竣工 開学記念日を6月1日に変更 |
| 平成3年(1991) 4年(1992) 6年(1994) 9年(1997) 10年(1998) 11年(1999) |
近藤不二学長就任 付属教育、研究施設として英語センター設置 7号館(山路ふみ子記念学習院国際文化センター)竣工 学習院女子短期大学最後の入学式 学習院女子大学開学 近藤不二女子大、短大学長就任 近藤不二学長退任 早川東三女子大、短大学長就任 卒業式 |
| 自由な留学生活に感激 |
|---|
| 桜友会スカラーシップ第3回生 榮谷明子 |
|
1996年3月学習院女子高等料卒業 1996年4月東京大学教養学部入学 現在東京大学教養学部文化人類学科在籍 1992年8月からl年間オランダ国アイントホーヘン市に留学 桜友会スカラーシップ制度第3回留学生として、1999年8月ミシガン大学留学 研究テーマは「日本の身体障害者について医療人類学からのアプローチ」 |
 右側が筆者 |
|
|
|
| 第15回 オール学習院の集い開催 |
|---|
遠ざかる 研究室や 花こぶし 淑子(俳句の会より)
21世紀「平成13年度 第15回 オール学習院の集い」が去る4月15日(日)に開催されました。昨年とは打って変わって今年はまさに春本番! 朝からうららかな陽気にめぐまれて10時の開場と共に正門は人出も上々。4時の閉会までに入場者は昨年を上回り8000余人。特に今年は子供の手を引く家族連れが目立ちました。 |
 |
| 新刊紹介 |
|---|
|


 ミシガン大学留学への道のり
ミシガン大学留学への道のり 著書・心にひびく共感のアプローチ
著書・心にひびく共感のアプローチ