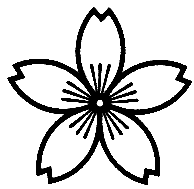

平成11年5月1日発行第74号より抜粋
 夢をつむぐオペレッタ 夢をつむぐオペレッタ |
 三角帽子のお屋根の幼稚園舎 三角帽子のお屋根の幼稚園舎 |
|---|
| 第17回経済学部講演会より 10年11月5日(木)於:記念会館 |
| 夢をつむぐオペレッタ ・・・オペレッタは大人の文化・・・ |
|---|
| 日本オペレッタ協会会長 寺崎裕則氏(31年政経卒) |
|
オペレッタと歌舞伎
オペラは1598年に、歌舞伎は1602年に東西で期を一にして総合芸術が生まれた。東西の光を当て合うと、オペラも歌舞伎も本質は同じで、表現方法が違うだけだ。それらは、耳と目と心の悦楽がある。特に心の悦楽は、人を感動させることであり、人を感動させることはドラマなのだ。 オペレッタの魅力と魔力
オペレッタは愛の百科事典、恋の展覧会などと言う。 大人の慰み
1855年にオッフェンバックによってパリで生まれ、1860年には"恋はやさしい野辺の花よ"の「ボッカチオ」で知られるスッペが、ウィーンで「寄宿学校」を作曲した。やがてヨハン・シュトラウスや「メリー・ウィドゥ」を作ったレハールが出てくる。19世紀末から20世紀初頭はハプスブルブ家が繁栄し没落していき、新しい産業革命によって新興ブルジョアジーが生まれていった。その時代のみんな爛熟した大人の社会が生んだ"大人の慰み"の文化がオペレッタなのだ。 21世紀はオペレッタの時代
戦後50年、日本は心を疎かにしてきたので、本物の文化が育っていない。文化は"心の福祉であり精神の糧"なのだ。 夢を紡ぐオペレッタ
心のゆとりの時代、若者が、少年時代に「大人の世界っていいなあ」と思うような、大人の素敵なソサエディが生まれてくれば本当に幸せだなと思う。 |
| キャンパス・ニュース・・・・ |
| 短大最後の卒業式
・・・使命を全うし、次世代への礎を作る・・・ |
|---|
| 女子大学教授 湯本和子氏(1回生) |
'99年3月19日、学習院女子短期大学は48回卒業生774名を最後に、1回生以来22,525名の卒業生を送り出し、その使命を全うした。この式場に、1回生を送り出された斉藤道香先生も出席下さったが、感慨深げなご様子であった。私も卒業生の名前を一人一人呼び上げながら、発展的転換ではあっても短期大学の名前が消えて行く淋しさと申訳なさをしみじみと感じていた。 |
・・・学び舎は永遠に・・・ |
| 小野寺由里子氏(第48回卒業生) |
平成11年3月19日は、天候に恵まれなかったものの、短期大学最後の卒業生として、無事に卒業式を迎える事ができました。 |
・・・短大最後の卒業式に招かれて・・・ |
| 18回生A.T. |
小雨けぶる3月19日、第48回卒業式に、卒後30年の18期生19名が参列させていただきました。 |
| 三角帽子のお屋根の幼稚園舎 |
|---|
昭和38年に設置されて以来の学習院幼稚園舎が新しくなり、本年2月に昭和寮跡地の仮園舎からお引っ越ししました。 |
| 新刊紹介 |
|---|
|


 書名:一週間でわかるJavaScript
書名:一週間でわかるJavaScript