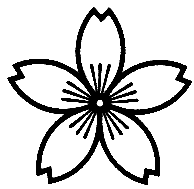

平成10年5月1日発行第72号より抜粋
 21世紀をめざしての日本の半導体産業 21世紀をめざしての日本の半導体産業 |
 「自分の頭で考える」訓練を 「自分の頭で考える」訓練を |
|---|
| 第16回経済学部講演会より 9年11月28日(金)於:記念会館 |
| 21世紀をめざしての日本の半導体産業 |
|---|
| (株)東芝常勤顧問(前取締役副社長)川西 剛氏(24年旧高卒) |
15兆円産業と言われる半導体産業は、今年が50年目の節目だ。米国でトランジスターがベル研究所で発明されて50年、日本で事業化されてから40数年になる。この20世紀を見て、半導体産業ほど特筆すべき産業は日本にはなかった。成長率、技術のイノベーション、国際化の広がり、全ての面で夢が多かったし、まだ夢のある事業はこれからもないと思う。こういう産業に携われたことは、私の大きな幸福だったと思う。 変革が起きている
21世紀を前にして変革が起きつつある。第一は、自己完結型のビジネスが困難になってきた。個人や、一つの組織、一つの会社、一つの国で全てを賄うことが出来なくなってきた。チームワーク、相互協力、異業種交流、国境を越えた協調等が避けられなくなった。 日本は米国に学べ
日本は農業社会で、村意識が強い。人材を企業に従属させ忠誠を誓わせ、その代わり手厚く保護し永久就職の様なぬるま湯に漬かっている面が多い。日本のカルチャーは物を作るHow to makeに特色があり、組織力で御輿を担いでワッショイワッショイというやり方だったから、クリエイティブなこと、何か新しい物を作るWhat to makeが弱い。こういう面では米国に太刀打ちできないと思う。 21世紀の半導体産業は
一つは、芭蕉の句に「先人の後を追うな、先人の求めたものを求めよ」というのがある。芭蕉が奥の細道で旅をした時に目的は先人がどういう道を辿ったかというのを探ったかも知れないが、実際は、自分で新しい世界を切り開いていった。半導体も同じで、50年経ったが、やはり何が求めるものなのかに重点をおくことだ。二つ目は、どんな小さなことでもそこで先ずトップになる。大企業でも中小企業でも、人のやらないことをやればトップになれる。大企業はそのニッチトップが沢山ある企業であり、中小企業はそれが少しの企業であると言うことだと思う。三つ目は、外部情報に敏感になることだと思う。色々な外とのやりとりの中で、外との苦闘の中で、自分自身を見出していかねばならない。 |
| 会員トピックス・・・・ |
| 日本のお酒と文化を楽しむ |
|---|
| 村田 淳一氏(36年経済卒) |
質、量共にナンバーワンと言われる銘酒の会を十数年間、手弁当で主宰していらっしやる村田淳一さん(36経済卒、元菓子問屋専務・現(株)ローソン顧問)をお訪ねして「日本の酒と食の文化を守る会」(旨い酒、美味しい料理を嗜む会)のお話を伺いました。 |
| キャンパス・ニュース・・・・ |
| 「自分の頭で考える」訓練を |
|---|
| 学習院女子大学教授 白井健策氏 |
社会に出てから40年以上もの間、新聞記者として働いてきました。学者ではないので研究業績なるものはありません。大学という世界そのものが、一種の異文化のようにさえ思えます。そういう人間が大学で何らかの貢献をするとしたら何ができるでしょうか。 |
| 新刊紹介 |
|---|
|


 書名:インとその看板のいわれ −イギリス・バークシャー州を中心に− バークシャー婦人会連盟編訳
書名:インとその看板のいわれ −イギリス・バークシャー州を中心に− バークシャー婦人会連盟編訳